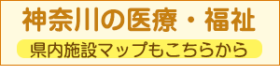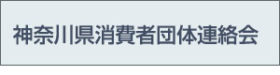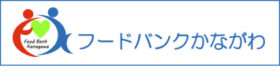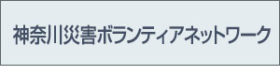2023年 全体会報告
| 日時 | 2023年5月11日(木)14時30分~14時50分 |
|---|---|
| 会場 | 神奈川県生協連会議室・zoomを使用したオンラインの併用 |
| 出席 | 天野 武(神奈川県建設労働組合連合会)、和久晴雄(神奈川公団住宅自治会協議会)、渡邉敬弓(神奈川県生活協同組合連合会)、山崎初美(コンシューマーズかながわ)、齋藤静子(環境保全型農業を推進するネットワーク)、野元摩里(新日本婦人の会神奈川県本部)、清水眞利(神奈川県母親連絡会)、清水百合子(横浜市消費者団体連絡会)、木村郁子(さがみはら消費者の会) 庭野文雄、田中知巳、佐々木陽子(事務局) |
| リモート出席 | 荒川美作保(神奈川県生活協同組合連合会)、有田芳子・柿本章子(コンシューマーズかながわ)、松﨑嘉子(横浜市消費者団体連絡会) |
| 欠席 | 三井敦子・伊藤淑子(神奈川県建設労働組合連合会)、大森規男(神奈川公団住宅自治会協議会)、照井携子(神奈川県母親連絡会)、多賀谷登志子(横浜市消費者団体連絡会)、 |
□司会:渡邉 敬弓さん
【神奈川県消費者団体連絡会2023年度全体会】
1.本日の出欠情報を事務局の佐々木より報告。
2.議案の提案と審議
会計監査報告
第3号議案 2023年度活動計画(案)
第4号議案 2023年度予算(案)
第5号議案 2023年度幹事・常任幹事・会計監査(案)
庭野事務局長より、第1号議案から第5号議案について報告、提案された。
第2号議案2022年度決算報告、会計監査については5月9日に神奈川公団住宅自治会協議会和久晴雄幹事、新日本婦人の会神奈川県本部 野元摩里幹事により神奈川県生協連事務所において監査を実施し、適正に処理されていたと報告した。
第5号議案では2023年度の幹事・常任幹事・会計監査の分担を以下の通り提案。
さがみはら消費者の会 木村 郁子
神奈川県消団連事務局長 田中 知巳
横浜市消費者団体連絡会 清水 百合子
なお、第5号議案2023年度幹事については、鎌倉消費者連絡会が現在空席となっているが、団体自体はまだ存続しており、今年度中に解散する予定のため、現段階では団体名は記載していること、また、神奈川県生協連よりパルシステム神奈川荒川美作保幹事の交代、コンシューマーズかながわ柿本章子幹事から田辺恵子幹事へ交代、さがみはら消費者の会ではあらたに中村訓幹事が加わることを報告した。
常任幹事については、これまでの順番の経緯をもとに2023年度は2022年度常任幹事から引き続き環境保全型農業を推進するネットワーク齋藤靜子幹事、新たにさがみはら消費者の会木村郁子幹事が常任幹事に、会計監査においては2022年度に引き続き神奈川公団住宅自治会協議会和久晴雄幹事、新たに横浜市消費者団体連絡会より清水百合子幹事となることで報告した。
以上、第1号議案から第5号議案について承認いただき本議案は成立した。
以上